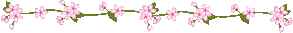
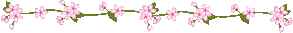
|
どこまでも続く桃色のアーチ。
天も地も空間さえも染めて、まるで世界を覆っているかのようだ。 時折舞い散る花びらは軽やかなワルツを踊り、新たな世界へと旅立っていく。 ・・・花に、酔いそうだ・・・・ 散り始めた桜の並木道を俺は歩いていた。 隣には戸惑い顔のマヤがいる。 無理もない。有無を言わさず強引に連れてきたのだから。 1時間前―――俺は聖からある報告書を受け取った。 それは彼をもってしても、その詳細を知るには半年もの時間がかかった国家的なトップシークレット。 俺はその書類を読み進めるうちに、ある事実を知った。 覚悟はしていたはずだった。 いつかはこのような日が来るかもしれないとおぼろげに感じてはいた。 だが、しかし・・・ 俺は思う以上に動揺している自分に呆然とした。 水城くんに連絡をして、この後のスケジュールは後日へと振り替えさせる。 ただ赴くままに車を走らせ、気づくとマヤのアパートへ来ていた。 「ちびちゃん、桜が満開だ。たまにはのんびり花見などいかがかな?」 「・・速水さん!?」 突然訪ねて来た俺に、マヤは目を丸くしていた。 何事かと混乱している彼女を、さっさと車に乗せて連れ出し・・そして今、桜の名所と言われる この公園を歩いているわけだ。 なぜそんなことをしたのか、正直なところ俺自身にも分からない・・・ 黙々と歩く俺に、マヤは声をかけようにもかけられないといった様子だ。 マヤには悪いが、俺は話をするつもりはなかった。 乾いた心から出る言葉など碌なものではない。 悪戯に彼女を傷つけたり、不快にさせることは避けたかった。 そうして公園の中を二人で歩くうちに、一本の見事な枝振りの桜の木が眼前に現れた。 「綺麗・・!」 今日初めて生き生きとした声を出したマヤは、その木を目指して駆けていく。 俺はその無邪気であどけない行動に、何やら力がフッと抜けるのを感じた。 手を上にかざし花を見上げるマヤの姿を眩しく感じ、目を細める。 「大都芸能の鬼社長が昼間に花見とは優雅なものだな」 ・・・聞き覚えのある懐かしい声が俺を呼びかけた。 「よぉ」 腰まで届く長いストレートの髪が、風になぶられて踊っている。 木の陰から現れたその男は、サングラス越しに俺を見つめていた。 「神・・」 何年ぶりの再会だろうか――― 記憶を手繰ろうとしたが、奴の変わらぬ不敵な笑みを見てそれを数えることの無意味さを知った。 オックスフォード大学で知り合った俺の唯一の友、神恭一郎。 端正な顔立ちに如才のない話術で、学内において彼を慕う者は多かった。 だが、その優しげな瞳の奥にあるのは野生の猛獣を思わせる光。 何かに対しての妄執に囚われ、それを狩ろうとするしなやかな獣の目だ。 しかし、それに気づく人間はごく一部だった。 彼の物腰の柔らかさがそれを巧妙に隠していたのだ。 そう、見抜けるのは彼と同じ激しさで負の感情を抱く者のみ――― 神もまた、俺に同じ光を見出したのだろう。 孤独を知り、それをバネに生きる者同志、妙にウマが合った。 「こんな所で何をしているんだ、探偵殿」 桜の木の下で佇んでいる男に俺は話しかけた。 奴は花の陰から一歩、俺の方へと踏み出す。 「お前のスカした顔が見たくなってな」 いつもながら口の減らない男だ。 だいたい人の顔をどうこう言えた義理か! ・・・おそらくはこういうものを似た者同志というのだろう。 「だが、あてが外れた」 ワザとらしく大仰に肩を竦め、残念そうに奴は言った。 「お前のそんな穏やかなツラが見れるとは思っていなかったぞ」 「それはこっちのセリフだ」 『穏やか』 ・・その言葉が似合うほどに、神の周りには温和な空気が取り巻いていた。 気配だけをみれば、まるで別人であるかのように。 探偵という、常に危険が隣り合わせにある職業に就いている男が醸し出す雰囲気とは到底 思えない。 いや、それ以上に奴の本質は切れ味の鋭いナイフであったはずだ――― 「神・・・お前に牙はもう必要なくなったのか?」 印象のままに口から滑りでた俺の疑問に、奴は透明な笑みを浮かべた。 それが、答えだった。 神が斜め後方へと視線を向け、その先にある一人の女・・マヤを見つめる。 マヤはこちらの様子に気づく気配もなく、飽きずに桜の大木を眺めていた。 「あの少女なんだな?」 神がただ一言、念を押すように俺に言葉を投げる。 何がと聞く必要はなかった。 何を言わんとしているのか、その一言で充分だった。 「そうだ」 俺は頷いた。 今まで誰にも言ったことのない想いをあっさりと肯定したのは、神の驚くほど真剣な表情に 引き摺られたからかもしれない。 「速水、欲しいものは手に入れろ。そして決して手放すな」 強い口調で奴が言う。 「お前は手に入れたのか?」 「あぁ。ようやくな」 常に何かを求め、戦い続けていた男には不似合いな、満足気な響きがそこにはあった。 「神!!」 よく通る、力のある声がヤツの名を呼び、場の空気を変えた。 舞い散る花びらの中、駆けて来るのは長い髪をなびかせたセーラー服の少女だ。 風を切るように走るその娘の手には一本の黒い筒が握られており、今日という日が卒業式で あったことを物語っている。 少女は駆け寄ると、神の腕の中へと勢いよく飛び込んだ。 「お待たせ、神!」 にっこりと笑う少女に、神は愛しみに溢れた眼差しで彼女を迎える。 この男がこんな表情をするとは・・・そして、それを見る時がこようとは。 「別れは告げてきたのか?」 「ああ。皆、待っていてくれた。全てを・・・託してきたよ」 どこか男性的な話し方をする、しかしそれがその容貌によく似合う凛々しさすら感じる少女だ。 彼女は神の言葉に切なげな表情を浮かべたが、次の瞬間にはその憂いを振り払い、強い意志の 瞳を抱く男に注ぐ。 「待ち人が来たのでな。そろそろ行くとしよう」 神は俺を振り返ると、別れに繋がる言葉を向けた。 佇む二人の姿は花のかけらの舞の中で儚げに映り、どこか現実感を損なわせる。 「いいか、速水。何者にも捕らわれるな。お前らしく生きろ」 桜が染め上げる空気の中で伝えられた神の言葉は、耳ではなく、まるで直接頭に・・心に響くよう だ。 「・・・ああ・・・」 目の前にあるのが掴むことの出来ない夢、幻のようで、不可思議な感覚に襲われた俺はそれだけを 言うのが精一杯だった。 神が俺の言葉に眼差しで頷く。 「では・・『さよなら』だ、速水」 「さよなら・・神・・」 さぁっ、と吹き抜ける風に花びらが舞い上がり、それは螺旋を描いて小さな竜巻を形成した。 その渦が治まったときには二人の姿はもうなかった。 「速水さん?」 いつの間にか、マヤが俺の横に来ていた。どうしたのかと小首を傾げている。 不安げに見上げる彼女の顔を見ているうちに、ふいに頬に一筋冷たいものが走り、それは音もなく 地面へと消えていった。 自然に手が動いた。支えと温もりを求めて。 「は、速水さん!?」 俺の腕の中でマヤが驚きの声をあげる。 「少し・・このままでいてくれないか?少しの間でいいから・・」 マヤは戸惑いながらも普段と違う俺を感じたのか、こくりと頷いた。 後日、俺は聖の提出した書類を、俺自身の手でシュレッダーにかけた。 それは政財界に通じている者なら誰もが知っている公然の秘密・・・政府によって闇から闇へと 葬られたある事件の全貌が記されていた。 日本を掌握し、軍事国家とせしめんとした世界的な組織があったこと。 その計画は水面下で何年も前から着々と進行し、正に水際で食い止められたこと。 そして組織の計略を、死を持って阻止した一人の私立探偵と一人の少女がいたこと――― ・・・神、お前は今、笑っているんだな? うるさい程に響くシュレッダーの音が止まった。 俺はスイッチを切り、背広を掴むと扉の向こうにある俺の戦場へと足を向けた。 <Fin> 速水さんの唯一の親友、神恭一郎が「スケバン刑事」の登場人物だということは有名ですが、 これはその最終回にからんだエピソードとなります。 「スケバン刑事」という作品を愛し続けている私にとって、20年以上もの間、胸に抱えていた話を こうして表現する機会を得たということは幸福と言う他ありません。 もっとも、文章力の不足は否めませんが、それは仕方がないということで。 ご存知ない方に簡単に「スケバン刑事」最終回を説明をしますと・・ 巨大な闇の組織『猫』の計略が人知れず阻止された半年後、学生刑事麻宮サキの母校では多くの 学生達が集っていた。そこにいるのは在校生だけではなく、日本中のあらゆる学校の生徒達。 彼らは行方不明になっているサキに会うことは出来ないかと、式が終わった後もひたすら待ち続けて いた。 「遅れてごめん!」 その期待に応えるかのようにサキは現れる。 彼女は皆に「後は頼んだ」と一言残し、愛用していた武器のヨーヨーを空へ向かって投げる。 そして恩師から渡された卒業証書を手に、笑顔で校門へと走り去っていくのだった。 しかし再会の喜びの直後、学生達はある事実を知ることとなる。 サキが半年前の戦いで、神恭一郎と共に命を落としていたということを。 そう、彼女は愛する友人達に、学校に、永遠の別れを告げに来たのだ――― ・・・というストーリーです。 |
 |
 |